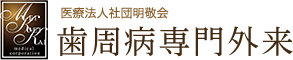歯周病と全身の関わり
歯周病が全身に及ぼす影響

歯周病が影響するのはお口の中だけと思われがちですが、実は全身の病気を引き起こすことがあります。
歯周病の原因である細菌は、お口の中から喉や血管を通じて体内に入りこみさまざまな臓器に運ばれます。運ばれた先の心臓や肺、肝臓なとで多様な疾患を引き起こす原因となることが分かっています。また、妊娠中の方には胎児や母体にも影響を及ぼすこともあります。
歯周病を予防するためにお口の中を綺麗にし衛生的な環境を整えることは、これらの全身疾患を予防のためにも重要なことです。入れ歯などの義歯の汚れも歯周病とほとんど同じ細菌ですので、義歯も天然の歯と同じように丁寧にお手入れをする必要があります。
歯周病と関連がある全身疾患
糖尿病
糖尿病が歯周病を引き起こすリスクもありますが、逆に歯周病が糖尿病を引き起こすこともあります。糖尿病と歯周病は相互に悪影響を及ぼすため、どちらもコントロールしながら治療と予防をする必要があります。
心臓疾患
歯周病の原因である細菌は、血管を詰まらせ動脈硬化や心筋梗塞を引き起こすことがあります。また、細菌が心臓まで運ばれ感染を起こすと心内膜炎の原因にもなります。
肺炎
高齢者で介護の必要な方や寝たきりの方は、飲み込むための嚥下機能が低下していることがあります。そのため、お口の中の唾液や細菌が気管に入りやすく肺炎を起こしやすくなります。
女性と歯周病の関係

歯周病は性別に関係なく起こる病気ですが、女性ホルモンとも密接に関係しています。そのため、女性はホルモンのバランスや体調の変化で歯周病にかかりやすいのです。
特に妊娠中は女性ホルモンが大量に分泌されるため、ある特定の歯周病菌が増殖しやすくなり、歯周組織の炎症が起こりやすくなります。また、つわりによって歯磨きや食事が十分にできなくなることもお口の中の環境を悪化させる原因にもなります。
その他にも、女性ホルモンが作り始められる思春期や女性ホルモンの分泌が低下する更年期も歯周病が進みやすいため、適切なケアを続ける必要があります。
妊娠性歯肉炎
妊娠の初期に見られる歯茎の腫れや出血が「妊娠性歯肉炎」です。女性ホルモンが増えることで起きるため多くの妊婦さんに見られますが、普段の正しい歯磨きで歯肉炎を予防することができます。出産後にホルモンバランスが落ち着くと共に治まってきますが、ケアができていないと歯周病まで悪化します。
低体重児出産(早産)
歯周病にかかると、歯周組織が刺激されて「炎症物質」を作ります。これらが歯肉の血管から血液中に入り、子宮まで達すると「低体重児出産・早産」の危険度を高めます。妊娠時に歯周病があると悪化しやすいため、妊娠に備えて治療をすませておくのが理想的です。