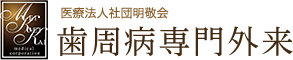歯周外科治療
歯周外科治療とは

歯周病の基本的な治療には、プラークを取り除くプラークコントロールや歯石を取り除くスケーリング、ルートプレーニングなどがありますが、それらの治療でも改善しない場合には、外科治療によって歯肉奥深くの歯石の除去、歯周ポケットの除去、歯周組織の修正を行い将来的に歯を少しでも長く保存させるための外科治療を行うことがあります。
歯周病は、1度進行が進むと簡単に直ることはありません。またひどく失われた歯周組織は、どのような治療法を用いても完全に元通りにするのは難しいのが現状です。手遅れの歯周病は治療できず歯を抜くしか選択肢がないこともあります。そうなる前に、早めに歯周病を発見し治療をすることがとても重要です。
歯周病外科治療の種類
歯周ポケット掻爬術(そうはじゅつ)
麻酔をして歯周ポケット内の歯石やプラークを除去する方法で、軽度の歯周病で歯周ポケットの深さが3~5mmの時に行います。
フラップ手術
歯肉剥離掻爬手術(しにくはくりそうはじゅつ)とも呼ばれ、麻酔をしてメスで歯茎を開きます。直接目で歯石を確認し完全に取り除き、歯の表面を滑らかに整えます。手術後に歯肉が治癒する過程で歯周ポケットがなくなります。
歯周組織再生療法
重度の歯周病により歯肉や歯槽骨が失われた場合に行う、歯周組織を再生を促す方法です。再生療法には「GTR法」と「エムドゲイン法」があります。
GTR法

歯肉を切開し、露出した歯根からプラークや歯石を除去します。ダメージを受けた歯周組織も取り除き、歯槽骨の清掃も行います。その後、メンブレンと呼ばれる保護膜で歯周組織が再生できるように保護します。こうして失われた歯周組織を回復させる治療法です。
※ メンブレンとは
歯科の治療だけでなく、人工血管や人工心膜など多くの医療器具として使用されている保護膜です。生体親和性が高く、安全な素材の一つです。
エムドゲイン法

手術の方法はGTR法とほぼ同じで、麻酔をかけて歯肉を切開し、歯根の表面を徹底的に清掃します。歯石や炎症部分を取り除いた後に、エムドゲインを塗り、切開した歯肉を元の状態に戻します。エムドゲインは、歯の発生過程のような環境を作ります。そのため、初めて歯が生えた時と同じように歯周組織にしっかりとした付着機能を持たせる再生治療法です。
※ エムドゲイン・ゲルとは
エムドゲインは、子供の頃に歯が生えてくる重要な役割のあるたんぱく質の一種のエナメルマトリクスデリバティブが主成分となっています。このたんぱく質は歯周組織の再生誘導材で、歯周組織の形成を促します。
骨移植法
骨移植法も、歯肉を切開し歯石や炎症部分を取り除いた後に、歯槽骨が失われた部分に自分の骨である自家骨や人工骨を移植します。自家骨の方が、安全性や身体との親和性が高く成功率が高くなっています。
動揺歯(ぐらぐらする歯)の暫間固定(T-FIX)
動揺歯とは
歯根周囲の骨が吸収・歯根膜(歯根と骨の間の隙間)が拡大し、ぐらぐらする歯、動く歯のことで、しっかり噛めない、硬いものがかめない、噛むと痛み、しみる、違和感などの症状がある。
動揺度検査で診断しますが、重度になると抜歯か、使えるところまで使う延 命処置になります。 軽度~中度は、早めに処置すれば、進行はSTOPできる、但し、歯石とりと 歯磨きだけでは治らないことがあります。
固定することにより骨の吸収をSTOP(動きが大きいと骨ができないため) 固定種類もいくつかあります。 歯の位置が変わるため、咬合調整は必須です

「暫間固定(T-FIX)の種類」
・接着材のみ
・細い針金のみ
・細い針金+接着材
・歯を削り込み+針金+接着材
でそれでも動く場合は、数歯一体型のかぶせものをつくる
但し、歯を削る必要があるので、要検討

歯を横に動かす原因を除去する以下の処置が必要です。
・かみ合わせの調整(早期接触の除去、臼歯離開させる等)
・歯ぎしり、食いしばり装置(ナイトガード)
・咬合力の分散(歯の本数が少ないため、咬合力の過剰負担になっている場合)
・歯の接触癖をなくす
経過観察
歯の動きを止めないと、骨ができてこない。最低6カ月はみていきます。
また3~4か月に一度はデンタルX線で状態確認しかみ合わせの調整をします。
その時に以下の3つを選択していただきます。
・このままか再度、固定を強化
・抜歯
・かぶせもので連結
ナイトガート

ナイトガードとは、寝ている間の歯ぎしりの治療の際に使用されるマウスピースです。 マウスピースは、歯ぎしりの治療で最も一般的に行われる治療方法です。 寝ている間に透明のプラスチック製のマウス ピース(ナイトガード)を歯に装着することによっ て、 歯や顎にかかる負担を軽減し、歯ぎしりの症状を軽減します。
噛み合わせ調整
かみ合わせの調整
骨の吸収が重度程、かみ合わせを弱くあてるように調整し、 骨がしっかりした歯に負担させ、骨の状態が良くない歯を長持ちさせるようにします。
また、他の歯より早く接触してしまう歯(早期接触)
上下歯の接触時間が長い歯
歯を横揺れを起こす場合など
以下の3つの顎の運動をチェック・調整します
①中心咬合位 (上下がしっかり噛む位置)
②側方運動(下顎を左右に動かす時)
③前方運動(下顎を前に動かす時)